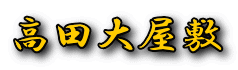
(たかだおおやしき)
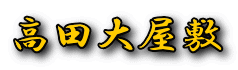
(たかだおおやしき)
国指定史跡(菊川城館遺跡群)
菊川市下内田

▲高田大屋敷は鎌倉御家人内田氏の地頭屋敷であったと考えられる遺跡である。
(写真・屋敷跡)
地頭内田氏の屋敷
|
菊川と上小笠川の合流点西側に高田大屋敷と呼ばれる史跡がある。土塁で四方を囲んだ中世初期の地頭屋敷を伝えるものとして貴重な歴史遺産となっている。 ここ菊川市下内田はかつて内田荘下郷と呼ばれ、平安時代末期頃から内田氏を名乗る武士が土着して地域を開発していた。この内田氏、伊豆狩野氏一族の工藤祐経の孫とされる武士で、内田致茂(むねしげ)という。鎌倉幕府の時代には内田荘下郷の所領を安堵された地頭御家人である。 承久の乱の後、後鳥羽上皇方から没収した西国の所領は幕府によって御家人らに与えられた。これを新補地頭という。内田致茂も貞応元年(1222)に北条義時から石見国貞松郷と豊田郷の地頭職を恩賞として給付された。内田氏は遠江と石見に所領を持ったことになる。致茂は嘉禎二年(1236)に嫡男致員に下郷の地頭職を譲り、この年没した。 二代致員は文永八年(1271)に所領を嫡男致直、次男致親に譲与したが後に悔返(くいかえし)を行って致親の子朝員に譲った。悔返とは一旦譲与した財産を取り戻す行為で、中世社会ではそうした権利が存在していた。当然のこととして三代の致直としては不満が残ったが、弘安八年(1285)の致員没後に朝員を養子とすることで内紛を回避した。 四代朝員は弘安九年(1286)から惣領として活動したが文保三年(1319)に致景に下郷地頭を譲り、石見の所領に移った。 五代致景は元徳三年(1331)には石見国豊田郷も継承した。南北朝の争乱期である建武三年(1336)から五年(1338)にかけては駿河や遠江における合戦に参加して活躍したが、康永元年(1342)以降は石見における合戦にその名をとどめており、遠江における内田氏の活動は記録に残されていない。内田氏は致景の代に父祖伝来の下郷の所領を放棄して石見の所領地へ移ったとされている。 下郷内田氏の遠江に於ける活躍時期は平安末期から南北朝の争乱期である暦応年間(1338-42)までである。高田大屋敷の遺跡と内田氏との関係は実証されていないが、中世初期の地頭屋敷の景観的特徴を有していることから地頭内田氏の屋敷跡に相応しいとされている。発掘調査の結果をみても中世後期の痕跡は確認されていないことから内田氏の活躍時期に合致する遺跡であるとされる。 |
 ▲説明板。文字が消えかかっている。 |
 ▲吉川神社の社叢と屋敷跡(手前)。 |
 ▲説明板の近くに盛土があるが市に問い合わせたところ、経緯不明の土盛で史跡との関連性はないとのことである。 |
 ▲屋敷跡の南側一帯。肝心の土塁に囲まれた居館跡はこの北側にある。 |
| ----備考---- | |
|---|---|
| 訪問年月日 | 2024年4月11日 |
| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |
| ↑ | 「高田大屋敷遺跡」他 |