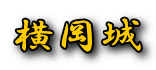
(よこおかじょう)
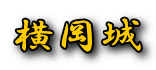
(よこおかじょう)
市指定史跡
島田市横岡

▲横岡城は明応の頃(15世紀後期)、鶴見氏の居城
であったが、今川氏親の軍勢によって落とされた。
(写真・茶畑となった城跡と井戸跡(中央の四角いくぼみ))
遠江侵略の血祭り
|
新東名高速道路の島田金谷ICの北西約700mの段丘上に横岡城跡がある。別に志戸呂城、鶴見城などとも呼ばれる。 この横岡城に関しては城主鶴見因幡守栄寿の明応五年(1496)の争乱のことが伝えられている。当初、鶴見氏は駿河今川二代当主範氏に仕えて掛川に館(掛川市城西)を構えていたとされる。しかし、応永二十六年(1419)以降の遠江守護は斯波氏が独占しており、この間に鶴見氏は斯波氏に属する道を選んだものと思われる。そして居住地を大井川西岸の志戸呂に移して横岡城を築いたとされる。志戸呂に移った年次や経緯は不明だが、背景に今川方の松葉城主河井蔵人成信との確執があったとの見方もされている。 さて明応五年(1496)である。この年の七月、今川氏親は長松院(掛川市大野)宛に乱暴狼藉を禁ずる旨の禁制を発した。長松院は松葉城主河井蔵人を開基とする寺院であり、氏親の叔父一訓和尚が住職であった。この禁制は今川氏が河井氏とその領域を保護する姿勢を鮮明にしたことを意味するものであったといえる。 この事態に驚いたのは東遠所在の斯波方、勝間田播磨守と鶴見因幡守であった。腹背に敵を受けては存亡にかかわる危機である。ここで二十年前の文明八年(1476)に今川義忠に滅ぼされたはずの勝間田の名が出てくる。この勝間田播磨守は多くは勝間田城主として説明されているがその素性に関してはよく分からない。長松院記中には榛原郡門原村に住せりと記されているという。門原とは桃原のことで勝間田城下にあたり、かつて勝間田氏の居館のあった所とされている。鶴見氏と同様に反今川であったのであろう。 ともかく勝間田、鶴見の両氏は合同で河井氏を討取る行動に出た。これが九月十日のことである。勝間田、鶴見の軍勢に松葉城を襲われた河井蔵人は城を落ちて長松院に逃げ込み、そこで自刃したとされる。河井蔵人の死を聞いた今川氏親は九月二十六日に長松院に采地を寄進してその菩提を弔ったとされる。 同時に今川氏親は軍勢を大井川東岸の相賀村(横岡城の対岸)に進め、おびただしい数の旗を立てて横岡城を威嚇した。「掛川誌稿」に「…大井河ノ東相賀村ニ偽旗ヲ張リ…」とあり、今でも国1バイパス沿いに旗指(はっさし)の地名が残っている。そして今川勢は密かに迂回して大井川を渡河したようで「…奇兵ヲ長者原ヨリ下シテ…」と横岡城の背後の高台から襲いかかかり、一気に城を落としてしまった。鶴見因幡守は今川勢に討取られ、奥方は井戸に身を投げて自決したという。嫡男大蔵は城を脱して出家、後に横岡の地に戻って観勝寺三世在仙太存和尚となったという。 その後、今川勢は氏親の軍師伊勢盛時(後の北条早雲)の指揮のもとに遠江侵略を続けて行くことになる。横岡城はその最初の血祭りにあげられたものといえる。 現在城跡のあった場所は「城之壇」と呼ばれているがほとんどが茶畑となっており、その中に奇跡的に井戸跡が残されている。 |
 ▲城之壇と呼ばれる段丘東端部が城址となる。 |
 ▲説明板。 |
 ▲城址の主要部は茶畑に開墾されている。 |
 ▲茶畑の中に残された井戸跡。 |
 ▲城址から長者原の台地を見る。 |
 ▲藪でよく分からないが城址南側の堀跡。 |
 ▲堀を隔てた南側の大手曲輪。 |
 ▲大手曲輪の櫓台上の祠。 |
| ----備考---- | |
|---|---|
| 訪問年月日 | 2025年3月9日 |
| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |
| ↑ | 「今川氏の城郭と合戦」他 |