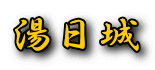
(ゆいじょう)
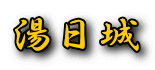
(ゆいじょう)
島田市湯日

▲湯日城は勝間田氏の支城であったとも当地支配の土豪の
城であったとも見られており、その詳細は不明な点が多い。
(写真・南側から見た城山)
高天神衆中山氏の城
|
富士山静岡空港の北側、湯日川の段丘上に築かれたのが湯日城である。築城者は明確でないが室町期には東遠の古くからの土豪・勝間田氏(勝間田城)の勢力圏下にあったことから同氏の支城であったとも見られている。 湯日城の東麓に養勝寺がある。開創は文明十三年(1481)、今川氏親の叔父である教之一訓和尚によると言われている。島田市公開の古文書「養勝寺古文書目録」によれば養勝寺開基は「中山兵庫助、二代同内蔵助氏長、三代同又七郎(是非之助)による…」とあり、湯日地域に中山氏の存在があったことがうかがわれる。中山兵庫助は今川氏の被官だったらしく天文(1532-55)の初め頃の人であったから養勝寺開基というより中興の武士であったかもしれない。 中山又七郎は後に是非之助と改名した。中山是非之助は高天神城主小笠原長忠の麾下の高天神衆の中にその名を留めている。いつ頃から高天神衆に加えられたのかは分からないが今川義元の時代からであったのかもしれない。永禄十一年(1568)、徳川家康が遠州入りするといち早く小笠原長忠は今川氏を見限って家康に臣従した。高天神衆も自動的に家康の臣下に加えられた。中山是非之助は浜松城の徳川家康に仕えたと伝えられており、それはこの時のことであったのだろう。 元亀元年(1570)、小笠原長忠と高天神衆は徳川家康に従って姉川合戦に参戦した。この合戦で高天神衆は姉川を渡河して朝倉勢を突き崩し、織田信長の勝利に貢献した。この戦いぶりを見ていた信長は「見事なり」と高天神衆の内の七人を激賞した。この七人は「姉川の七本槍」と呼ばれ、このなかに中山是非之助が入っていた。 天正二年(1574)、高天神城は武田勝頼に攻められて開城、城は武田のものとなった。城兵は立ち退くこととなり、徳川に付くも武田に付くも自由とされた。中山是非之助は城主小笠原長忠らと共に甲州へ行き、武田滅亡後は小田原北条氏に仕えた。北条氏滅亡後は浪人して三河岡崎に至り、老衰のうえ病死したと伝えられている。 現状は茶園、果樹園の耕作放棄地となって藪化して踏み入ることも困難な状況である。 |
 ▲城山の北側に農道の入口が見える。 |
 ▲かつての農道入口であるが城山全域が藪化して立入りは困難である。 |
 ▲右が城山、左の高台は富士山静岡空港の滑走路である。 |
 ▲今川家臣中山氏の開基と言われる養勝寺。 |
| ----備考---- | |
|---|---|
| 訪問年月日 | 2025年1月23日 |
| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |
| 「島田市公開古文書目録」より | |
| ↑ | 「静岡県の中世城館跡」他 |