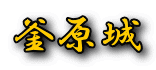
(かまっぱらじょう)
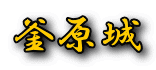
(かまっぱらじょう)
御前崎市新野

▲釜原城は南北朝期に落城したとの伝説を残しているが、最終的には天正期の
高天神城をめぐる武田・徳川の抗争期に武田側によって改修されたものとみられている。
(写真・本曲輪跡)
武田の出撃拠点
|
御前崎市の新野地区には同時期に整備されたと思われる城跡が密集している。八幡平城、舟ヶ谷城、天ヶ谷城、そしてここ釜原城である。また八幡平城の北1.5kmの菊川市との境に武田勢の塩買坂陣場跡がある。いずれの城も最終的には天正二年(1574)以降に高天神城をめぐる徳川勢との抗争のなかで武田勢によって改修整備されたものと見られている。 この新野地区には鎌倉期以前より横地氏(横地城)の支族新野氏が勢力を張っていた。この新野氏は南北朝期を境に今川系の新野氏に取って代わられることになる。釜原城の南東山麓にあった聖道寺(昭和47年廃寺)に伝わる「聖道寺縁由記」に、南北朝初期の戦いで落城したという伝説があり、このことから城主を横地系新野氏の一族に擬する説があるという。この落城伝説と今川系新野氏の入部との関連は不明である。さらに戦国期の今川系新野氏と釜原城の関係も不明である。 城跡の東麓の住宅地を「殿之谷」と呼び、かつての居館跡と見られている。現在ではこの一画に訪城者用の駐車場が設けられており、ここからハイキングコースが設定されている。約10分ほどで電話中継塔の建つ二の曲輪に達する。そして二の曲輪の北西方向に堀切があり、その先に本曲輪がある。堀切の北側に土橋状の道があり、本曲輪と繋がっている。この道はかつて茶畑であった時代の農道の名残りとも見られている。本曲輪からさらに、尾根道を進むとその先に出曲輪がある。 釜原城の北650mほどに天ヶ谷城がある。天ヶ谷城には武田流の遺構が見られ、天正前期の高天神城をめぐる武田と徳川の抗争に際して武田勢の拠点となったとされている。このことから、釜原城も天ヶ谷城と連携する武田勢の出撃拠点となり、高天神城が武田勝頼によって落城した後はその後方支援の拠点として機能したものと思われる。 |
 ▲訪城者用の駐車場。 |
 ▲駐車場に立てられた説明板の縄張図。 |
 ▲ここから城跡まで徒歩約10分である。 |
 ▲住宅地の外れ「殿之谷」から見た城山。電話中継塔(黄矢印)の建つ所が城址である。 |
 ▲山道を登りきると二の曲輪である。右側の柵内に中継塔が建っている。 |
 ▲二の曲輪の標柱。 |
 ▲二の曲輪の先に堀切と土橋状の道があり、本曲輪へ繋がっている。 |
 ▲本曲輪跡。訪れる人も稀なのであろう、夏草が生い茂り、歩くのも難儀であった。 |
 ▲平成19年(2007)当時の本曲輪跡。 |
 ▲同じく二の曲輪跡。一面の茶畑であった。 |
| ----備考---- | |
|---|---|
| 訪問年月日 | 2007年6月16日 |
| 再訪年月日 | 2024年7月4日 |
| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |
| ↑ | 「静岡県の中世城館跡 他 |